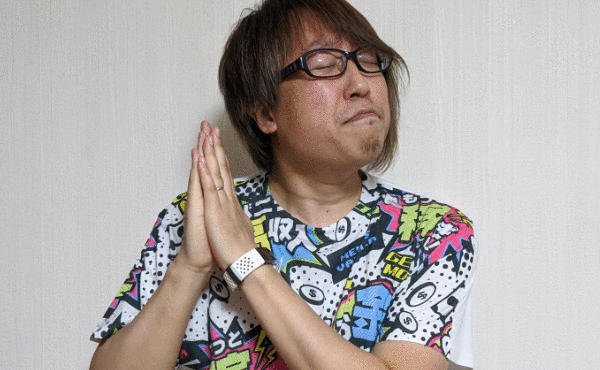身内に取り組んでいる人がいることもあって,最近のWebにおける「情報レコメンデーション」については色々と考えさせられます.これまでに読んだ本や他の情報源の中から気になる部分をピックアップしながら,考えをまとめてみます.
Web上で「情報レコメンデーションをしようとしている人」「情報レコメンデーションされたいと思っている人」「日々,面白い情報に出会いたいと思っている人」たちに,何か少しでも考えるキッカケを与えられたら嬉しいです.
さりげなくおせっかいな情報レコメンデーション
お笑いコンビ千鳥の「桃太郎」というネタを見るとよく分かる通り,「面白いことを言います」と言ってから人を笑わせるのは,それ自体がネタになってしまうほど難しいものです.情報レコメンデーションに関しても同じではないでしょうか.「あなたにピッタリの情報をおすすめします」と言ってしまうと,ハードルが上がりますよね.例えば*LOVE IS DESIGN* – はてなブックマーカー御用達ツールまとめでまとめられているような,ソーシャルブックマークの過去の情報を利用したレコメンデーションサービスを使ってみようと思ったら,いやがうえにも期待が高まります!また,そもそもユーザは常に「何かオススメしてちょーだい!」と思っているわけではないので,たとえ素晴らしいサービスに出会えたとしてもブラウザを開くたびに自分からサービスのページにアクセスしたりはしないでしょう.
その点,レコメンデーションシステムの代表例とも言えるAmazonの「この商品を買った人はこんな商品も買っています」は本当に上手です.ページの下の方にちょこっと見えていて,おすすめが外れだったとしても無視されるだけで,それっぽいものが出てきたら感謝されるんです.おすすめとして掲示される情報の取捨選択をユーザに任せることで,ハードルを下げているのでしょうね.だから前述のソーシャルブックマークからのレコメンデーションサービスも,推薦結果をRSSとして配信するなどすれば利用価値が高まるはずです.実際にそうしているサービスもありますね.
そのキーワードとは、
「meddle / おせっかいであること」
(中略)
そもそもWebのサービスなんてものは、「そんなのなくていい」というところから、日常的に使ってもらうための価値を提供できるように「おせっかいしていく」ものなのです。まして今のWeb2.0時代、「既に何がしかの代替サービスは必ず存在してたり、ブランドが確立しつつある」という状態でサービスを始める以上、良いもの作れば誰かが見てくれるであろう、という前提で作るものではないですし、本当に効果が出るか、などはわからないと思います。だって「おせっかい」なんですから。だからこそ真剣に「おせっかいの質」を追求したいものです。
そう,レコメンデーションにはおせっかいという言葉がよく似合います.「頼んでもいないのにおすすめしてくる」ぐらいが丁度いいです.「だけどうざったくない」これはもう見せ方の問題ですね.さりげなくもおせっかいに,それっぽいものをおすすめしてほしいものです.
これからのWebに求めるもの
ボクらはWebに何を求めているのでしょう.仲間の研究によれば,現在,Web上には300億をこえるWebページが存在しています.もはや全体像を想像することすらできないスケールです.こうしている間にも,Webは成長を続けています.そんなWebに,ボクらは何を求めるのでしょう.
「○○○が欲しい!」という欲求の大部分はGoogleが満たしてくれました.ウェブ進化論を始めとした様々な場所で言われている通り,Webのこれまでの発展は検索エンジンによって支えられてきたと言って差し支えないでしょう.
だけど,検索エンジンが見せてくれるのは「これまでの歴史」としてのWebです.じっくりと時間をかけて吟味された「良いもの」だけがボクらに届きます.検索クエリに対して,長い歴史の中で最も優れているであろうものが届きます.これは,その分野における権威を生み出してしまうことになります.
なんだか、昔、西部邁が比喩的表現として、「情報の微分化と情報の積分化」みたいな事を書いていたようなことを思い出した(ふと、日本の左翼は、情報の積分(=歴史的経緯)という視点が抜けているからダメなのかもなとか思ったが)。インターネットサービスとして考えると、「はてなブックマークは、情報を微分化して、今一番話題になっている情報を割り出して、トレンド情報をユーザーに提供する」といった感じか。また、「Wikipediaは、情報を整理して積分化し、言葉の定義をユーザーに提供する」といえるかもしれない。
ボクはここで言われている「Wikipedia」を「検索エンジン」に置き換えて捉えています.検索エンジンは,若くて勢いのある輩を活躍の場に登場させてくれるわけではありません.「今,すごく勢いのあるもの」「流行りモノ」は検索エンジンでは探せないのです.そもそも,何が流行っているかが分からなければ,検索キーワードを入力することすらできません.
大きな量的変化によって,情報は「そこに置いてあるもの」から「流れていくもの」に変わりつつあるような気がします.技術的には,パーマリンクなどによって「ずっとそこに置いてある」ことになるのですが,他の情報の量が膨大過ぎるためにそこにあるものさえも流されてしまうようなイメージです.情報はこちらから能動的に取りにいくものではなく,向こうから流れてきて受動的に消化するようになってきています.通り過ぎて見失ってしまった情報はなかなか探し出すことができません.それらの中から,気になったものを繋ぎ止めておけるのがソーシャルブックマークでしょうか.
今のWebを楽しむためには,面白いものを探し当てる能力よりも,たくさんのものが流れてくる場所を見つけ,その流れの中から面白いものを選び出す能力が重要です.同時に,面白くないものは見捨てる覚悟も必要です.こういうのをスルー力って言うんですか.分かりません.
Popular pages on del.icio.usやはてなブックマーク – 人気エントリーは,まさにたくさんのものが流れてくる情報の源泉ですね.何が流れてくるのか,ジャンルは本当に分かりませんが,複数のユーザに支持されているということで「一定の質が保たれた何か」が流れてくると言えましょう.つまりこれらは,誤解を恐れずに言えば「メディア化」しているのです.
自分にとって不必要な情報が流れてくることもありますが,それは当然でしょう.すべてのユーザにとって必要な情報なんてありません.いらない情報は無視してしまえばいいだけです.情報に対して能動的になればなるほど,外れを引いたときの落胆は大きくなるので,ついつい文句を言ってしまいたくなる人はもっと受動的なスタンスで見つめたらいいと思います.受動メディアの代表格であるテレビを見ているときに「全部の番組がオレ様好みであれ!」とは思わないでしょう.
ボクは最近,自分でも自覚するくらいにWeb上の情報に対しては受動的で,むしろ絶対に自分からは検索しないようなコンテンツに出会えたときの方が喜びが大きかったりします.たまたま面白かったらそれでいいなぁと思っています.2ちゃんねるの掲示板は全く見ないボクでも,2ちゃんねるで爆発的に盛り上がっているスレの内容は面白かったりするんです.無数の情報の中から「これは間違いなくお前にピッタリだ!」というものをひとつ出されるより,「こんなの面白いよー」ぐらいの緩さで10個くらいおすすめされて,1個でも面白ければけっこう楽しめます.ボクは適合率よりも再現率を求めていることになりますね.
この辺りの話が面白い本なりエントリなりにリンクしておきます.
そこで重要になってくるのが「ノイズ(雑音)」である。「ユーチューブ革命」後のマスメディアの生き残る道は、情報の偏食を防ぐためにいろんなノイズを提供し続けることだろう。ユーザーが自分では絶対に選ばない、検索しない、見つけられない情報を大量に提供することにマスメディアの意義が存在する。
YouTube革命 P.177 第六章 ユーチューブ後の世界 「個人メディアのロングテール」
(前略)ウェブは、求めれば求めるままに情報を提供してくれるが、それは必ずしも社会にとって有用なものばかりではないからだ。
スイッチをつければ自動的に情報が流れるテレビと違い、ウェブではその情報の選択はすべてユーザーにかかっている。クエリーやクリック、投稿するコメントの内容など、その一挙一動で触れられる情報は変化する。そして、いくつかのウェブサイトでは、自動的に特定方向に誘導していくパーソナライゼーション機能やリコメンデーション機能によって、情報のベクトルはいつしか方向が狭められていく。それは便利であるのは間違いないだけに喜んで使われるだろうし、逆に専門性を高めるには役立つ 。
一方でそれはセレンディピティ(思いがけないものの発見)をなくし、新たな出会いを失うことにもつながる。あらかじめ予測された範囲のものだけが推奨され、自らの思考も意図せずして規定されていく可能性もある。そう考えると、単純な楽観は控えざるを得ない。
グーグル・アマゾン化する社会 P.246-P247 第7章 「民主主義」によってつくられる“主体性ある思考” 「セレンディピティの喪失」
(今現在の)パーソナライゼーションでは受け取る情報が一極集中してしまうと。「あなたが欲しい(と言っている(とわたしが思っている))情報」だけを届けていたら、肉ばっか食べて太ってしまうよ、たまには野菜も食べなさい、にんじんバーグにしてあげるから、ということか。なんだそれは。
セレンディピティは今のWebを考える上でひとつの大きなトピックになると思っています.ソーシャルブックマークの人気エントリが自分好みのページだらけになったら逆に要注意!でも文中のセレンディピティの訳「思いがけないものの発見」は,セレンディピティ – Wikipediaの記述とはニュアンスが違いますね.どっちの意味で使っていこうかな.何か知っている人がいたら教えてください.
そろそろまとめたい
きちんと言葉にならない想いを,しかも慎重に書いてきたので疲れました.最後にボクの独り言を並べておきます.あまり考えずに書きます.
- はてブのホッテントリとは,緩く付き合おう.ありがたかったらお礼を言う.ありがたくなくても文句を言わない.くらいの距離で
- Web上のノイズをとことんまで楽しもう.「調べ物をするときに便利!」なんてのはついででよい.ヒマ人の理論だ
- 受動メディアとしてのWebに感謝しよう.YouTubeには面白い動画がたくさんあるってことはみんな知っている.だけど,どうやってそれを探したらいいかは分からない.だからカウントダウンチューブとかLast.tvみたいに(いい意味で)適当に選んだものを流してくれるとありがたい
- テキストに比べて映像や音楽はレコメンデーションに向いている.これもやっぱり受動メディアだからだ.テキストは能動的に読まなきゃいけない.映像や音楽は見ているだけ,聞いているだけでもよい
- かっちりしたレコメンデーションより,緩いくらいが丁度よい.かっちりしすぎると,自分の知っているものしか出てこない.ボクみたいに偏った世界に生きていると,Amazonがおすすめしてくれる本が,過去に読んだ本だらけになる.「よくできているなぁ」「当たっているなぁ」とは思うけど,役には立たない.結局,本屋さんをフラフラ歩いて目に付いた本を買う.セレンディピティ!実はグーグル・アマゾン化する社会もそうやって選んだ本なのだ.大当たりだった例です
- 検索エンジンをWebの積分,ソーシャルブックマークやブログ上を流れるメディアをWebの微分とするなら,その間くらいの何かが欲しい.「この期間,こんな話題が,こんな風に発展していった」これは自分の研究テーマに成り得るぞ
- ソーシャルブックマークは集合知と成り得るのか.はたまたメディアと成り得るのか.少なくとも「データベース = 集合知」ではないと感じる.これはまた別のエントリを立てる必要があるなぁ.もやもやしている
- きっとこのエントリを投稿したあとで「あ!アレ書いていない!」ってのがあるんだろうな
長文になりました.乱文ですが言いたいことは言えたので満足です.考えを文章化することで頭もスッキリしました.ありがとうございました.